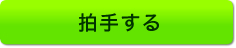メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
どうでも雑記
石部の棚田 Ⅳ 「稲刈り」
2022年10月10日 
テーマ:伊豆の生活
実りの秋10月上旬は米の収穫、稲刈りです。稲作作業の最後になる稲刈りは重労働だが、収穫の喜びと「新米」をいただけることに感謝しながら稲刈りをする。
地域の棚田保存会の人達はもとより、棚田保存に協力いただいている棚田のオーナー、稲作体験のボランティアで参加した家族連れや一般の人達、そして近隣の学生など、大勢の人が集結する。
大型コンバインが田んぼの中を行ったり来たり走り回る。刈り取られた稲の稲穂は自動でもぎ取られ「モミ」になる。
稲ワラの方は、昔は縄とかムシロの材料になる他、野菜の根回りに敷くなど生活の中でいろいろ使われる貴重なワラだったが、現在はコンバインの後ろから細かく刻まれて、そのまま田んぼに撒かれて肥料となる。
昔は稲刈りの時期になると、子供の手も借りたいほど忙しく、学校も農繁休暇というのがあって、家族総出の収穫作業だった。
自分家の稲だけが田んぼに残ると、みっともないということで、地域一斉に稲刈りをするから、田んぼはお祭りのように賑やかだった。
現在はコンバインの運転手と2人で出来る仕事なので、いつの間にか終わっている。棚田は大型機械が入らないのでそうはいかない。
黄金色に実った稲は、田植えのときと同じように腰をかがめて、今度は一株握っては根元で切りながら、前に進む。この作業も腰にくるので大変な作業です。
昔の農家の人達は歳をとると皆、腰が「くの字」に曲がっていたが、こんな過酷な作業をしたのが原因なのか。O脚で腰が極端に曲がった農家の年寄りを見ると、いつも考えてしまう。この棚田の稲作を指導する地域のお年寄りにも腰の曲がった方が多い。
秋晴れの下、棚田保存会からの挨拶の後、それぞれの棚田に入る。涼しい秋風が吹き抜ける中だが、流れる汗をぬぐいながら稲をカマで刈り取ります。
こうして地域外の多くの人達が集い、笑いや掛け声、子供たちの声も賑やかに聞こえる中で、棚田の稲刈りが行われる。
稲を刈り取ったら、稲穂を乾燥させるために小さく束ね、逆さにして写真のように田んぼの中に「掛け干し」で天日干しにする。
早春から実りの秋まで、八十八回の手を掛けた米づくりを通じて、自然の恵みなどを学び、稲作を通して人と人との交流を、世代を超えて深める。
眼下に広がる駿河湾の景色も楽しみながら秋のひとときを過ごす。(つづく)
コメントをするにはログインが必要です
潮風さんへ、
棚田の米は美味しいのが分かっていても、大型機械が入らず、昔と同じ手作業なので重労働ですが、それが米作りの体験です。
そんな重労働のため、少子高齢化で後を継ぐ人がいなくなり長年、原野になっていました。
棚田に戻すのに3年ぐらいかかって、今でもまだ荒れているところがあり、修復を続けています。
kenは西伊豆にセカンドハウスを持って、13年ほど二地域生活をしていて、この棚田を知り参加していました。
今は西伊豆から撤退し、以降は棚田オーナーとして参加しています。
2022/10/11 17:24:26
未来へつなぐ棚田の保全と景観
おはようございます。
平地の田んぼよりはるかに苦労が多かろう棚田の作業。
植え付けから収穫までわかりやすい説明でよく理解できました。
大変さもまた楽しいことも一方で伝統文化の継承とか癒しの景観、多岐にわたる棚田の一年間。
保全に係る方々には改めてご苦労様の気持ちです。
2022/10/11 09:53:16
喜美さんへ、
そうですよね、胸椎が曲がっている人は見かけるが、腰が曲がっている人は昔と比べたら極端に少ないですね。
今でも田舎の方に行くほど腰の曲がった老人が多いです。食生活も多少の要因になっていると思いますが、やはり重労働から腰が曲がったり、O脚になっているように思います。
そういう人たちも80,90歳も元気でいられる人が多いことは立派ですね。
2022/10/10 16:41:10