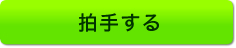メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
どうでも雑記
石部の棚田 Ⅱ「代掻きと田植え)」
2022年10月05日 
テーマ:伊豆の生活
山から湧き出る冷たい水も温む4月下旬、いよいよ「代掻き(しろかき)」が始まる。
田越しでうなった田んぼに水を張って、土をさらに細かく砕きながら、丁寧にかき混ぜて、稲を植えられるように土の表面を平らにする作業です。
昔は牛を使っての作業だが、貧乏で牛を飼えない農家では鍬と代掻き用の農機具を使っての手作業だから重労働だった。
この棚田も極狭場所は手作業だが、小さな耕運機を使っている。
一緒に、田越しのときに固めた畔に、更に土を盛ってしっかりと畦付けをしたら、その上に軟らかい土で畦塗りをして仕上げるが、鍬の裏面を使って壁塗りのような作業になる。
そして、田んぼの準備が整い5月に入るとすぐに、田植えの季節到来です。
棚田には時おり駿河湾から吹き上げる西風が冷たく感じるが、海に向かった南西斜面は暖かい。
周辺の山は新緑色になり、山桜が咲き、野鳥の声が聞こえる。畦には春のたんぽぽやイヌフグリが咲き、棚田はモノトーンからスプリングカラーになる。
「春の小川はサラサラ行くよ…」なんて小学校唱歌があるが、それよりも小さな流れが棚田のいたるところで音を立てて流れ落ちる。
その水の音は山間に広がる棚田が春を奏でているように全体で聞こえる。
静かだった棚田は春の賑やかさがましてくる。
暖かい週末に「田植え」が行われるが、機械が入らないので田植えは全て手作業です。
未耕作となった歴史ある棚田を再現保存しょうと心ある人たちと、同意する次世代の若者たちにも協力を得て、勧められている。
このことで一番嬉しいのは地元農家のお爺さん・お婆さんたちでしょう。先祖から引き継がれてきた棚田の復活だから、この日ばかりは明るく元気です。
ボランティアで参加した一般と高校生の若者たちを受け入れる地元農家の老人たち、手取り足取りの実践指導です。
手に持った稲束から3本ぐらい取っては、足元に落とした物を拾うような姿勢で、苗を土に刺し込みながら後ろ下がりに進みます。
普段しない姿勢に腰痛が我慢できず作業が止まる。それでも大変さよりも皆は田植えを楽しんでいる。
お茶休憩や昼食休憩あり、一日通して棚田の田植え作業が、世代を超えた交流の深まる場でもあり、お互いに貴重な体験となる。
田植えの終わった田んぼには、どことなく残る足跡と、バラバラな向きで植えられている稲だが、幾日もしないうちに稲は生え揃って奇麗な棚田になる。
棚田に生息するモグラやサワガニ、春の暖かさで孵化する昆虫たちも、これを機に一斉に活動し始めることだろう。
(つづく)
コメントをするにはログインが必要です
めのうさんへ、
めのうさんのブログから感じることは自然と暮らす自然を守る。そのことを通じて仲間や友達とを大切にすっる。そんなことを強く感じています。
生きていく上でなにが大切かな…と考えると、人を守る、環境を守る、文化を守る。そんなことを考えながら身の丈で出来そうなことを、シニア人生で楽しめればと思っています。
今は老いと共に行動力が落ちましたが、気持ちだけは持ち続けたいと思っています(笑)
めのうさんも手植えの経験があるのですね、懐かしく故郷の昔を思い出して頂けて嬉しく思います。ありがとうございます。
2022/10/06 10:25:48
手植え
私も小学校の頃、近所寄り合いの田植えには「1行がけ」で、大人(3行がけ)に混じってやりました。
Ken さんはさつまいも掘りとかも子供達となさいましたね。若い人達が土に触って仕事をする経験をすることはとても大切な事だと思います。
そういう活動を計画される勇士さん達に脱帽です。
2022/10/06 05:13:16
芝桜さんへ、
ご苦労されたとは言いたくありませんが、農家は皆同じでした。だから都会に出たという人も多いと思います。
大変な作業ですね、経験者でなければ分からないことが書かれています。よ~く分かります。
米つくりは八十八も手がかかるというから大変ですね。
棚田はご存じのように狭いので、3人ぐらいが並んで、長い竹の棒を横に渡して、それに沿って稲を植えると、1歩下がって竹の棒も移動します。
なので農家さんのような速さではないので楽しくやっています(笑)
*田植えか稲刈りに合わせて、情報を取り棚田見学に行くと昔を懐かしく思い出すでしょうね、
2022/10/05 19:07:38
この光景に
嫁入り直後の田植えを思い出しました。
非農家から嫁ぎ、何もかも初めての事ばかり。線にそって植えるのも出遅れるため濁って見えず、かなり出遅れるため迷惑の掛け通し。田植え稲刈りとそこだけ参加の私が、義父の畔作りや水の管理、雑草取りの苦労を知ったのはかなり後からの事でした。
棚田といえば、去年日南市にある酒谷の棚田を観に行きました。
2022/10/05 17:43:31