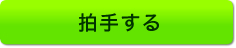メニュー
最新の記事
テーマ
- お裾分け ( 1 )
- イベント ( 3 )
- トリビア ( 6 )
- プレゼント ( 7 )
- 事故・事件・災害 ( 7 )
- 友 ( 6 )
- 回想 ( 13 )
- 圭君 ( 8 )
- 季節 ( 31 )
- 心理学 ( 1 )
- 感謝の気持ち ( 9 )
- 日常 ( 7 )
- 時事 ( 5 )
- 歳時記 ( 24 )
- 言霊・メッセージ ( 30 )
- 雑感 ( 4 )
カレンダー
月別
- 2016年08 月( 1 )
- 2016年07 月( 1 )
- 2016年06 月( 1 )
- 2016年05 月( 5 )
- 2016年04 月( 7 )
- 2016年03 月( 4 )
- 2016年02 月( 2 )
- 2016年01 月( 7 )
- 2015年12 月( 1 )
- 2015年11 月( 6 )
- 2015年10 月( 5 )
- 2015年09 月( 20 )
- 2015年08 月( 3 )
- 2015年07 月( 3 )
- 2015年06 月( 2 )
- 2015年05 月( 1 )
- 2015年04 月( 3 )
- 2015年03 月( 1 )
- 2015年02 月( 2 )
- 2015年01 月( 5 )
- 2014年12 月( 1 )
- 2014年11 月( 3 )
- 2014年10 月( 2 )
- 2014年04 月( 1 )
- 2014年03 月( 4 )
- 2014年02 月( 3 )
- 2014年01 月( 3 )
- 2013年12 月( 3 )
- 2013年11 月( 3 )
- 2013年10 月( 5 )
- 2013年09 月( 6 )
- 2013年08 月( 2 )
- 2013年07 月( 4 )
- 2013年06 月( 13 )
- 2013年05 月( 9 )
- 2013年03 月( 3 )
- 2013年02 月( 6 )
- 2013年01 月( 6 )
- 2012年12 月( 4 )
- 2012年11 月( 1 )
心 どまり
蓮(はちす)の露 (迷い・悟り編)
2015年09月05日 
テーマ:言霊・メッセージ
文政九年(1826年)秋の事です。
良寛様は、二十年程住まわれていた国上山(くみがみやま)国上寺(こくじょうじ)の五合庵から、ふもとの乙子神社境内の社務所(乙子草庵)に移り、十年の年月が経過していました。
親交の有った三島郡輪島村嶋崎(現長岡市)の能登屋木村元右衛門の援助を受け、木村家屋敷内に有る小舎に移り住む事に成ったのです。
貞心尼はそれ以前から、木村家とはお付き合いが有ったらしく、元右衛門の妻宛てに、文政十年(1827年)卯月(旧暦4月)15日付で、文を送っています。
「当分、柏崎(閻王寺)には帰らぬつもりにて、幸いこの程
福嶋と申すところに、空庵の有候まま当分そこを借りる
つもり・・・」
貞心尼は遠まわしに、
「今度福嶋に住む事に成りましたので、良寛様がお立ち寄りに成られましたら、知らせてくださいね!」
と言う様な意味合いでしょうか!
良寛様に会いたいと言う、熱意や一途さとも受け取れますが、ちょっとちゃっかりしたおねだり上手とも!
良寛様の弟子遍澄が雪の降る前に、良寛様を乙子草庵から木村家にお連れなさったのも、高齢な良寛様を心配されての事でしょうが、木村元右衛門と共に、良寛様に貞心尼を会わせる準備だったようです。
良寛様は、その様な周囲の気配を知ってか、
「木村家の小舎が狭い!」
などとおっしゃって、寺泊の密蔵院に行ってしまわれたのです。そのお留守の時に、貞心尼が訪ねて来たと言う訳です。
帰り際、貞心尼は木村家に、良寛様に持参したお土産の手作りの手毬と歌を、託されたとも伝えられています。
文政十年(1827年)秋、良寛様70歳・貞心尼30歳の時に、木村家の小庵で、おふたりは初めて逢う事が出来まして、木村家に数日間滞在しております。
お逢い出来た喜び、嬉しさと共に、毎夜遅くまで続けられた熱い語らいの後、良寛様は二人を包む、遙かな高みから照らしている秋の月の視点を、歌にしたのです。
『 白たえの ころもでさむし 秋の夜の
月なかぞらに 澄みわたるかも 』
〔大変お心のこもった修行のお話に夜も遅くなり〕
(意)夏衣の袖あたりが、肌寒いほどの秋の夜です
が、月は凛として冴え、中空に澄み渡ってお
ります。
『 向かひゐて 千代も八千代も 見てしがな
空行く月の こと問わずとも 』
(意)向かい合って、良寛様の事だけを見ていたい
と思っておりますのに、お月(仏)様の事など
尋ねないで下さい。
良寛様が贈られた歌の返歌で、貞心尼は、
「空の上の仏様の事など、今は考えたくも有りません。」
と、軽く否してしまわれました。
貞心尼様も、大胆な事を言われたものですね!
彼女とて、仏門に入った尼さんですので、良寛様が提示なさった『月』が何を指すのか解らずに、こう歌った訳でもないでしょうに!こうなっては仕方ありません。
良寛様も、Yes!の歌を返しています。
『 心さえ かはらざりせば はふつたの
たへずむかはむ 千代も八千代も 』
(意)貴方が心変わりをしない限り、這う蔦が樹木
にしっかりと絡みつくように、千年でも万年
でも向かい合う事にしましょう!
貞心尼様の 勝ち〜!! 一本勝ちデス!!
良寛様は、珍しいほど性格が真っすぐな一人の女性に出逢われたのです。
いよいよ予定していた滞在日数も終わり、
「いつでも、お訪ね下さい!」
そう良寛様に言われて、別れて来た貞心尼でしたが、その後すぐに柏崎の閻王寺に修行に行く事となり、自由に良寛様を訪ねる事が出来なくなってしまいます。
貞心尼の訪問を、心待ちになさっていらした良寛様はと言いますと、良寛様の方が我慢できなくなり、こんなお歌で催促(?)していらっしゃいます。
『 君やわする 道やかくるる このごろは
待てど 暮らせど おとずれのなき 』
(意)貴方は忘れてしまったのでしょうか?
それとも、私の庵までの道が雑草に覆い隠さ
れて、解らなくなってしまったのでしょうか?
待てど暮らせど貴方は訪ねて来てくれません。
『 ことしげき むぐらのいおに とぢられて
身をば 心に まかせざりけり 』
(意)日常の雑事が重なり、粗末な庵に閉じ込められて
お逢いしたいのですが、心のままに、自由に
行動する事が出来ないのです。
貞心尼は、とりあえず言い訳をした後、正直に心に迷いが有る事を訴えたのです。
良寛様に会おうと決めた時から、漠然とした不安が彼女の心の中に、生じていたのではないかと思われます。
実際にお逢いしてみた良寛様は、想像していた以上に素晴らしく、魅力的なお人だった事で、離れていると良寛様の存在の大きさに、改めて気付かされた貞心尼でした。
お二人とも仏門に帰依している身、守らなければならない戒律も厳然とあります。
「どの様に二人の関係を結び、育てて行けば良いのかしら?」
貞心尼は、良寛様に逢いたい気持ちを抑えて、修行に励むのでした。
『 山のはの 月はさやかに てらせども
まだ晴れやらぬ 峰のうすぐも 』
(意)山の上の月(仏様・良寛様)は、こうこうと照
らしておりますが、私の心の中にはまだ迷い
が有るのです。
貞心尼の迷いは、彼女自身が払うより他に方法がない事を知りつつ、良寛様は一所懸命に歌を贈り励まします。
しかし良寛様御自身も、
「七十を超えようとする老いた禅僧と、三十そこそこの
未熟な尼がこの先どうなるのだ!これで良いのか?」
と言う懸念は、中々晴れなかったようです。
逢いに来ない貞心尼に、良寛様は続けさまに歌を贈っています。
『 身をすてゝ 世をすくふ人も ますものを
草のいほりに ひまもとむとは 』
(意)自分自身を捨てて、人々を救おうと日々努力
していらっしゃる人もいると言うのに、自分
の庵で閑を求めるとは、どういう事でしょう!
良寛様は、外聞も無く駄々っ子の様に、わざとすねて見せています。何の音さたもない貞心尼に、揺さぶりを掛ける様に次の歌です。
『 久方の 月の光の きよければ
てらしぬきけり から(唐)もやまと(大和)も 』
(意)月の光が清々しく、唐の国も大和の国も、
世界中を照らしておりますよ!
[昔も現在も、嘘も誠も!]
そして、「さあ〜!これでどうだ!」とでも言いたげに、追い打ちを掛けて来ます。
『 はれやらぬ 峰のうすぐも たちさりて
のちの光と おもはやすけき 』
(意)晴れていない峰のうすぐもが去った後の、
月の光を思わないのですか? 君は!
しかし貞心尼は、心を動かされなかったのです。
いくら頭では解っていても、心が伴うのにはいくらかの『時間』と言うものが、必要な場合も有ります。
秋から冬へ季節が移り、厳しい修行のうちに迎えた新年と共に、いつしか貞心尼の心の中にも、確固たる信念(悟り)が芽生えて来ていたのです。
『 この生き方を、生きよう! 』
続きは、『遷化編』にて!
お立ち寄りありがとうございます。
コメントをするにはログインが必要です