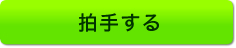メニュー
筆さんぽ
「終活」つづく
2023年12月24日 
テーマ:テーマ無し
Sさんは、自分の意志が実現されるかどうか心もとないと思っている。
どうだろうな。
どうしたものだか。
(あしたにつづく)
ぼくは常識的と思われることを言うよ、と注釈をつけた。
たとえば「葬儀は残された者がけじめをつけるための別れの儀式」といわれ「あくまで生きている者のためにある問題だ」と思うのだ。
Sさんにとって、これは、世間とうまく折れ合って生きている人たちが常識としている考え方で、
常々、「常識人と自称する人」から聞かされている話だよと鼻白むふうだった。
「延命処置」については、ぼくの亡くなった母の話をした。
母は病がすすんで朦朧状態であった。口にしたものを飲み込む力もないし、医師の話では、生きていくには胃や鼻にパイプを通して食べ物を直接流し込む方法しかないとの説明であった。
家族が集められた。兄は病で臥せっていたので、姉妹のほか「男」はぼくひとりである。姉が「男のあなたが決めなさい」といったふうのこという。いつも「男尊女卑」にがまんならないとぶつくさ言っていたのにと言おうと思ったが、のんだ。
どう決めたかは、ここでは省かせていただく。
みんなであれやこれやと話し合い、最終的には、ぼくが医師に話をした。
つまり、こういうことはマニュアルがあるわけではなし、「その場のなか」で決めるしかない。だから、今すぐ決定する必要はないし、その場になって考えても、遅くない問題だから、そっとしておけばよいと言った
「だが」とSさんは考える。
この世には、「世俗社会」の中では生きづらいと感じ、独りになって初めてくつろぐことができるというタイプの人間もいると思っている。そして、そういう人は周囲と波風を起こしたくないから、黙って世の慣行に従っているだけだという。自分はそうしたくないとも言う。
加えてSさんは
「葬儀無用」の遺言を残して死んでいる思想家や作家も多い。「延命処置」についても、点滴のチューブを自ら引き抜いて死んでいった作家もいると力説するように言う。
「きれいにまとめた人」もいる。
ぼくが知っているのは、「わたしが一番きれいだったとき」の詩人、茨木のり子さんである。
79歳のときに、自宅で脳動脈瘤破裂によって急逝したのり子さんを、訪ねてきた親戚が発見する。きっちりと生きることを心がけたのり子さんらしく遺書が用意されていた。(夫とはすでに死別していた)
「私の意志で、葬儀・お別れ会は何もいたしません。この家も当分の間、無人となりますゆえ、弔慰の品はお花を含め、一切お送り下さいませんように。返送の無礼を重ねるだけと存じますので。〈あの人も逝ったか〉と一瞬、たったの一瞬思い出して下さればそれで十分でございます」
わかってきたこともある。
Sさんが、葬儀無用にこだわるのは、儀礼の形式だけを重んじることが、死者を弔うことになるのか、これもやはり、生きている自分のけじめのためなのだろうかと考えている。
加えて、自分の葬式が想像できないという不安もある。
困るのは「これが正しい」と信じこみ、人はそれぞれ「事情」を抱えていることに目が届かない「我執にとらえわれて」いる人がいることだろう。
生涯現役を誇りにする人間がいる一方で、隠者志願の人間もたしかにいる。
どちらも排除するべきではなく、排除は歴史を振り返るまでもなく、「暗黒の時代」をつくる。
「オレは自分の葬式に数千人を集めてみせる」と自慢する生涯現役組がいる一方で、Aさんは誰にも知られずに静かに死んでいくことを幸福と考えている。自分の葬儀によって他者の生活を乱したくないという気持ちもある。
それはそれで、基本的人権をもちだすまでもなく、自由であろう。
そして、「終活」に「公式」などがありようもなく
人の数だけ「死に方」があるように
一人ひとり、それぞれの「終活」の考え方が
あってもよいとも考えている。
ではこう言えばいいだろうと、ぼくは話した。
Aさん、「世間の慣例に従え」ではなく、世俗の常識を超越して自らの信念を貫いたらいい。
この国における冠婚葬祭事情ときたら、誰が見ても「お話にならない」の一語に尽きるのだから。
制度というものが、社会的に認定されている行動様式であるとしたら
葬儀は、「制度疲労」のなかにいるといっていいだろう。
そしてこうしめた。
Sさんの息が止まったその瞬間から、Sさんは何も論じることはできない「無」の世界にいることになる。
「無」は、現在の何物も所有しない。
だれにでもやって来るものを
桜の季節になれば、花が舞うように
春のおだやかな空のような気分で
ごく自然に受け止めればいいではないか。
きっと、きれいに散るにちがいない。
終活とは脈絡なく、若いころのことを思い出した。そのころ付き合っていた女友だちに言われた。
嫌いなことを好きになるのと
好きなことを嫌いになるのと
どっちがむずかしい?
ぼくはたぶん、好きな人は嫌いになれないよ、とこたえたと思う。
コメントをするにはログインが必要です