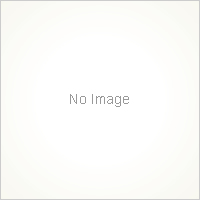メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
- 2023年06 月( 10 )
- 2023年02 月( 9 )
- 2023年01 月( 2 )
- 2022年12 月( 11 )
- 2022年11 月( 11 )
- 2022年09 月( 1 )
- 2022年08 月( 8 )
- 2022年06 月( 1 )
- 2022年05 月( 5 )
- 2022年04 月( 9 )
- 2022年02 月( 5 )
- 2022年01 月( 28 )
- 2021年11 月( 1 )
- 2021年10 月( 12 )
- 2021年09 月( 13 )
- 2021年08 月( 18 )
- 2021年07 月( 30 )
- 2021年06 月( 45 )
- 2021年05 月( 11 )
- 2021年03 月( 1 )
- 2021年02 月( 38 )
- 2021年01 月( 8 )
- 2020年12 月( 13 )
- 2020年10 月( 20 )
- 2020年09 月( 20 )
- 2020年08 月( 22 )
- 2020年07 月( 14 )
- 2020年06 月( 28 )
- 2020年05 月( 13 )
- 2020年04 月( 39 )
- 2020年03 月( 41 )
- 2020年02 月( 42 )
- 2020年01 月( 28 )
- 2019年12 月( 1 )
- 2019年11 月( 4 )
- 2019年10 月( 5 )
- 2019年09 月( 4 )
- 2019年08 月( 11 )
- 2019年07 月( 35 )
- 2019年06 月( 19 )
- 2019年05 月( 26 )
- 2019年04 月( 17 )
- 2019年03 月( 17 )
- 2019年02 月( 6 )
- 2019年01 月( 40 )
- 2018年12 月( 13 )
- 2018年11 月( 19 )
- 2018年10 月( 12 )
- 2018年09 月( 16 )
- 2018年08 月( 43 )
- 2018年07 月( 39 )
- 2018年06 月( 38 )
- 2018年05 月( 34 )
- 2018年04 月( 34 )
- 2018年03 月( 36 )
- 2018年02 月( 15 )
- 2018年01 月( 6 )
- 2017年12 月( 11 )
- 2017年11 月( 6 )
- 2017年10 月( 16 )
- 2017年09 月( 15 )
- 2017年08 月( 1 )
- 2017年05 月( 6 )
- 2017年04 月( 9 )
- 2017年03 月( 17 )
- 2017年02 月( 9 )
- 2017年01 月( 40 )
- 2016年12 月( 7 )
- 2016年11 月( 1 )
- 2016年10 月( 7 )
- 2016年09 月( 11 )
- 2016年08 月( 1 )
- 2016年07 月( 8 )
- 2016年06 月( 12 )
- 2016年05 月( 10 )
- 2016年04 月( 4 )
- 2016年03 月( 14 )
- 2016年02 月( 40 )
- 2016年01 月( 33 )
- 2015年12 月( 12 )
- 2015年11 月( 29 )
- 2015年10 月( 11 )
- 2015年09 月( 7 )
- 2015年08 月( 23 )
- 2015年07 月( 14 )
- 2015年06 月( 30 )
- 2015年05 月( 45 )
- 2015年04 月( 39 )
- 2015年03 月( 15 )
- 2015年02 月( 20 )
- 2015年01 月( 49 )
- 2014年12 月( 60 )
- 2014年11 月( 33 )
- 2014年10 月( 11 )
- 2014年09 月( 22 )
- 2014年08 月( 35 )
- 2014年07 月( 67 )
- 2014年06 月( 42 )
- 2014年05 月( 38 )
- 2014年04 月( 62 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 43 )
- 2014年01 月( 51 )
- 2013年12 月( 32 )
- 2013年11 月( 26 )
- 2013年10 月( 11 )
- 2013年09 月( 36 )
- 2013年08 月( 79 )
- 2013年07 月( 72 )
- 2013年06 月( 68 )
- 2013年05 月( 57 )
- 2013年04 月( 59 )
- 2013年03 月( 46 )
- 2013年02 月( 73 )
- 2013年01 月( 114 )
- 2012年12 月( 96 )
- 2012年11 月( 21 )
- 2012年10 月( 55 )
- 2012年09 月( 34 )
- 2012年08 月( 34 )
- 2012年07 月( 67 )
- 2012年06 月( 90 )
- 2012年05 月( 97 )
- 2012年04 月( 108 )
- 2012年03 月( 104 )
- 2012年02 月( 120 )
- 2012年01 月( 93 )
- 2011年12 月( 74 )
- 2011年11 月( 68 )
- 2011年10 月( 77 )
- 2011年09 月( 80 )
- 2011年08 月( 62 )
- 2011年07 月( 79 )
- 2011年06 月( 87 )
- 2011年05 月( 91 )
- 2011年04 月( 70 )
- 2011年03 月( 64 )
- 2011年02 月( 69 )
- 2011年01 月( 135 )
- 2010年12 月( 104 )
- 2010年11 月( 86 )
- 2010年10 月( 57 )
- 2010年09 月( 52 )
- 2010年08 月( 98 )
- 2010年07 月( 73 )
- 2010年06 月( 58 )
- 2010年05 月( 32 )
- 2010年04 月( 52 )
平成の虚無僧一路の日記
「恵日寺縁起」
2020年03月12日 
テーマ:テーマ無し
磐梯山麓の大寺に「恵日寺(えにちじ)」という寺がある。平安時代の初め、最澄と論戦を張ったという法相宗(奈良興福寺)の学僧「徳一」の木像と墓がある。史実的には「徳一」の創建と思えるが、『恵日寺縁起』では「弘法大師(空海)」の創建となっている。知名度の高い「空海」の方が良かったからだろう。『恵日寺縁起』によれば「当山は平城、嵯峨、淳和、白河、四皇帝の勅願所にて、弘法大師の御開基にして、鎮護国家の霊場なり。磐梯(いわはし)山には 魔物が住み、祟りを成すので病悩山と呼ばれていた。この国(会津)は、日々 霧に閉ざされ、俗に霧ケ里とも呼ばれた。大同元年(806年)、月輪、更科の二荘が一夜にして湖水となり、人民多く溺れ死す。悪風日々吹き、日月の光を見ることなく、五穀実らず、万民嘆き悲しみ給い、京都に奏聞す。そこで空海が使わされ、加持祈祷を行って病悩山の悪霊を鎮め、山を磐梯(いわはし)山と改め、寺を建てた。さて、この「一夜にして湖水となり、月輪、更科の二荘が水没した」という記述から、「磐梯山」が噴火したという説が横行している。どの本にも、ガイドブックにも「磐梯山の噴火により猪苗代湖ができた」と書いてある。しかし「縁起」には「噴火による」とは書いてない。また、地質の調査でも、噴火があったという痕跡(火山灰の堆積)は認められない。これは大地震で猪苗代湖が陥没してできたことを記していると私は考える。さて、『恵日縁起』では、弘法大師の後、法相宗の「得溢(徳一)」が、天皇の勅によってこの地に来、大師の後を継ぐ」としている。平安新興仏教の真言宗「弘法大師」の後に、旧奈良仏教の法相宗「徳一」が継ぐとはおかしな話。徳一開基だったとしても、いつの頃からか、「恵日寺」は弘法大師空海の真言密教の寺となっている。であるから、開祖を弘法大師にしたのであろう。
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません