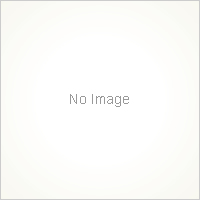メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
- 2023年06 月( 10 )
- 2023年02 月( 9 )
- 2023年01 月( 2 )
- 2022年12 月( 11 )
- 2022年11 月( 11 )
- 2022年09 月( 1 )
- 2022年08 月( 8 )
- 2022年06 月( 1 )
- 2022年05 月( 5 )
- 2022年04 月( 9 )
- 2022年02 月( 5 )
- 2022年01 月( 28 )
- 2021年11 月( 1 )
- 2021年10 月( 12 )
- 2021年09 月( 13 )
- 2021年08 月( 18 )
- 2021年07 月( 30 )
- 2021年06 月( 45 )
- 2021年05 月( 11 )
- 2021年03 月( 1 )
- 2021年02 月( 38 )
- 2021年01 月( 8 )
- 2020年12 月( 13 )
- 2020年10 月( 20 )
- 2020年09 月( 20 )
- 2020年08 月( 22 )
- 2020年07 月( 14 )
- 2020年06 月( 28 )
- 2020年05 月( 13 )
- 2020年04 月( 39 )
- 2020年03 月( 41 )
- 2020年02 月( 42 )
- 2020年01 月( 28 )
- 2019年12 月( 1 )
- 2019年11 月( 4 )
- 2019年10 月( 5 )
- 2019年09 月( 4 )
- 2019年08 月( 11 )
- 2019年07 月( 35 )
- 2019年06 月( 19 )
- 2019年05 月( 26 )
- 2019年04 月( 17 )
- 2019年03 月( 17 )
- 2019年02 月( 6 )
- 2019年01 月( 40 )
- 2018年12 月( 13 )
- 2018年11 月( 19 )
- 2018年10 月( 12 )
- 2018年09 月( 16 )
- 2018年08 月( 43 )
- 2018年07 月( 39 )
- 2018年06 月( 38 )
- 2018年05 月( 34 )
- 2018年04 月( 34 )
- 2018年03 月( 36 )
- 2018年02 月( 15 )
- 2018年01 月( 6 )
- 2017年12 月( 11 )
- 2017年11 月( 6 )
- 2017年10 月( 16 )
- 2017年09 月( 15 )
- 2017年08 月( 1 )
- 2017年05 月( 6 )
- 2017年04 月( 9 )
- 2017年03 月( 17 )
- 2017年02 月( 9 )
- 2017年01 月( 40 )
- 2016年12 月( 7 )
- 2016年11 月( 1 )
- 2016年10 月( 7 )
- 2016年09 月( 11 )
- 2016年08 月( 1 )
- 2016年07 月( 8 )
- 2016年06 月( 12 )
- 2016年05 月( 10 )
- 2016年04 月( 4 )
- 2016年03 月( 14 )
- 2016年02 月( 40 )
- 2016年01 月( 33 )
- 2015年12 月( 12 )
- 2015年11 月( 29 )
- 2015年10 月( 11 )
- 2015年09 月( 7 )
- 2015年08 月( 23 )
- 2015年07 月( 14 )
- 2015年06 月( 30 )
- 2015年05 月( 45 )
- 2015年04 月( 39 )
- 2015年03 月( 15 )
- 2015年02 月( 20 )
- 2015年01 月( 49 )
- 2014年12 月( 60 )
- 2014年11 月( 33 )
- 2014年10 月( 11 )
- 2014年09 月( 22 )
- 2014年08 月( 35 )
- 2014年07 月( 67 )
- 2014年06 月( 42 )
- 2014年05 月( 38 )
- 2014年04 月( 62 )
- 2014年03 月( 52 )
- 2014年02 月( 43 )
- 2014年01 月( 51 )
- 2013年12 月( 32 )
- 2013年11 月( 26 )
- 2013年10 月( 11 )
- 2013年09 月( 36 )
- 2013年08 月( 79 )
- 2013年07 月( 72 )
- 2013年06 月( 68 )
- 2013年05 月( 57 )
- 2013年04 月( 59 )
- 2013年03 月( 46 )
- 2013年02 月( 73 )
- 2013年01 月( 114 )
- 2012年12 月( 96 )
- 2012年11 月( 21 )
- 2012年10 月( 55 )
- 2012年09 月( 34 )
- 2012年08 月( 34 )
- 2012年07 月( 67 )
- 2012年06 月( 90 )
- 2012年05 月( 97 )
- 2012年04 月( 108 )
- 2012年03 月( 104 )
- 2012年02 月( 120 )
- 2012年01 月( 93 )
- 2011年12 月( 74 )
- 2011年11 月( 68 )
- 2011年10 月( 77 )
- 2011年09 月( 80 )
- 2011年08 月( 62 )
- 2011年07 月( 79 )
- 2011年06 月( 87 )
- 2011年05 月( 91 )
- 2011年04 月( 70 )
- 2011年03 月( 64 )
- 2011年02 月( 69 )
- 2011年01 月( 135 )
- 2010年12 月( 104 )
- 2010年11 月( 86 )
- 2010年10 月( 57 )
- 2010年09 月( 52 )
- 2010年08 月( 98 )
- 2010年07 月( 73 )
- 2010年06 月( 58 )
- 2010年05 月( 32 )
- 2010年04 月( 52 )
平成の虚無僧一路の日記
大同年間に何があったのか
2020年03月12日 
テーマ:テーマ無し
平安時代の初め「大同」という年号がある。西暦806〜810年。平安宮(京都)遷都を行った桓武天皇の後「平城天皇」と「嵯峨天皇」の御世。この「大同年間に創建された」と伝える寺が東北の各地にある。また、東日本大地震で明らかになったが、「大同年間」に大地震や噴火があったとする伝承が各地にある。那須連峰の茶臼岳、尾瀬ケ原の燵ガ岳、蔵王の刈田岳、そして会津磐梯山の噴火。そして、それを鎮めるために建てられたという「恵日寺」『勝常寺」他、茨城県の雨引千勝神社、早池峰神社、赤城神社、いわき市の湯の嶽観音、富士宮市の富士浅間神社、京都の清水寺、奈良の長谷寺。香川県の善通寺をはじめとする四国遍路八十八ヵ所の1割以上が大同年間の創建と伝えている。さらに、神楽の起源も大同二年作。それだけではない。秋田県の阿仁銀山、高根金山、吹屋銀山をはじめとする各地の鉱山の開坑も、大同年間。兵庫県・生野銀山の正式記録は「天文十一年(1542)開坑」となっているが、伝承では大同二年である。おまけに八溝山や森吉山などの鬼退治伝説。加えて、肘折温泉ほか、温泉にまつわる伝承も「大同年間」というのが多い。ところが、大同年間に、火山の噴火や津波、旱魃など天変地異があったとする証拠は見つかっていないたのだ。それなのになぜ「大同年間」なのか。大同年間とは「平城天皇」の世である。桓武天皇崩御の後即位したのは「平城天皇」。その名前が意味するごとく、794年、桓武天皇によって都は奈良(平城宮)から京都(平安宮)に遷都されたばかりなのに、その子である「平城」は、奈良へ都を戻すことを画策した。これは、臣下の反対にあって、在位わずか3年で弟の「嵯峨天皇」に位を譲ることとなる。また、坂上田村麻呂の“蝦夷征伐”が終わったのも大同の直前だった。そして、弘法大師空海が、唐から帰国したのが大同元年なのである。まさに、大同年間は、坂上田村麻呂によって、東北まで朝廷の威光が拡大した年であり、平城天皇は全国に観察使を派遣し、地方情勢を調べさせたり。全国に「鹿島・香取」などの軍神を祭る神社を建てている。福島県の中央には「田村郡」があり、また阿仁銀山の開坑なども、田村麻呂の功績となっている。加えて、弘法大師空海を迎えて、京都に清水寺を創建し、真言密教の加持祈祷力を利用して、病弱だった「平城天皇」は 全国の寺社に自分の健康祈願の祈祷をさせたのだった。ところで、空海が帰朝したのは「大同元年(806)」と言われるがはっきりしない。帰朝したばかりの空海の真言密教が即、都で迎え入れられたとは考えられない。空海が重用されるのは次代の「嵯峨天皇」によってである。であるから、全国各地の「大同伝説」は、はるか後世の人々が、空海と大同年間を結びつけて、作り上げ、広めていったものと考えられる。その役回りを担ったのが、山岳信仰と密教を集合させた「山伏」であった。磐梯山も湯殿山も、富士山もみな「山伏による山岳信仰」によって支えられてきたのである。
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません