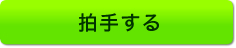メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
- 2023年12 月( 1 )
- 2022年01 月( 3 )
- 2021年12 月( 18 )
- 2021年11 月( 11 )
- 2021年10 月( 16 )
- 2021年09 月( 15 )
- 2021年08 月( 7 )
- 2021年07 月( 6 )
- 2021年06 月( 9 )
- 2021年05 月( 14 )
- 2021年04 月( 2 )
- 2021年03 月( 11 )
- 2021年01 月( 1 )
- 2020年10 月( 8 )
- 2020年09 月( 3 )
- 2020年08 月( 3 )
- 2020年07 月( 4 )
- 2019年10 月( 4 )
- 2019年03 月( 1 )
- 2019年02 月( 1 )
- 2019年01 月( 1 )
- 2018年11 月( 2 )
- 2018年10 月( 1 )
ひろひろ48
清く貧しく
2021年12月11日 
テーマ:テーマ無し
「清く貧しく映しく」清貧の考え方で、ネットで調べると、関西の阪急グループが東京進出のとき、東京宝塚劇場を建設し東京進出の趣意書にあったらしい。
江戸時代、戦国時代が終わり、平和が訪れ、身分制度はあったものの、自然災害による飢饉を除けば、ほぼ概ねそれなりに豊かな生活、人生を送れるようになった。多くの文化、芸能、歌舞伎、人形浄瑠璃、落語、祭り、浮世絵、小唄、縁側で将棋とか、楽しんだり、それと一生に一度はお伊勢参り、など、圧政に苦しんだというより、平和な世で生活も楽しんでいたようでもある。とにかく、飢饉がなければ、とりあえずは、なんとか食べていけた時代。
大東亜戦争、太平洋戦争の戦前も、庶民は清く貧しく美しかった。贅沢をしない、とりわけ、贅沢な食事をしない日本人は、「清く、貧しく、美しく」生きていた。
昨日の朝刊のコラム「あけくれ」から:
母とホイドby 香川 テイ子(76歳)
102歳で天国に召された母の思い出です。私が小学生のころだったか、木枯らしの吹くある日、ホイドが玄関で「何かくう物を・・」と話しかけてきました。田舎の青森では物もらいのことをホイドと呼びました。素足にゴムぞうり。あまりにもみすぼらしい様子で、急いで母を読ビンました。
母がリンゴを渡すと、彼は「リンゴはウメイけど、すぐ腹が減る」。母は「うんだねー。ちょっと待って」と家の中へ。
戻ってきたその手には、みそをまぶした大きなおにぎりが2個。新聞紙でくるみながら「気ぃつけてな、カゼっこひかないでね」。彼は「アリガトウゴス」と頭を下げ立ち去りました。
「なりたくてホイドになったわけじゃないよ。生きてればいろいろあるべ」とつぶやいた母の姿は忘れられない。子ども心にじんわり温かみを感じました。
そんな私も後期高齢者の仲間入り。体の不自由な夫とリウマチを患っている私だが、生きていかなくてはと念じるこのごろです。
<引用以上>
ホイドって、どこかできいたことがあるような。青森とか東北地方で、育ったわけじゃないので。同じように物もらいの意味で、ほいとと言っていたような。。「ほいと」は、仏教用語が語源だとか、広島弁だとか、諸説あるようです。それはそうと、日本人の多くが農民、漁民で、まだまだ地域の助け合いとかがあった時代の話か?
コメントをするにはログインが必要です